
- ホームページに関するお問い合わせ
- 050-3645-3907
COLUMN
お役立ちコラム
COLUMN
お役立ちコラム

電子カルテの三原則とは、厚生労働省が定めた「真正性」「見読性」「保存性」の3つの原則を指します。電子カルテを始めとした医療情報を電子保存する際に、守るべきルールです。医療機関が守るべき事項について、厚生労働省からガイドラインが制定されています。
しかし、ガイドラインはわかりづらく、実務やシステム構築の面で何に気をつければよいかわかりにくい担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、電子カルテの三原則についてわかりやすく解説します。各原則の具体的な実践方法から対応策まで、医療現場ですぐに活用できる方法を説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次

電子カルテの三原則とは、厚生労働省が策定したガイドラインで示される「電子保存の三原則」を指します。
電子カルテの普及に伴い、厚生労働省は1999年に電子媒体での医療情報保存に関するガイドライン(※1)を策定しました。電子カルテを含む医療情報を保存する際には、以下の3つの原則を守る必要があると定められています。
電子カルテを導入するすべての医療機関では、三原則を理解し、遵守する必要があります。
※1法令に保存義務が規定されている診療録及び診療諸記録の電子媒体による保存に関するガイドライン等について│厚生労働省

電子保存の三原則に違反した場合、直接的な罰則規定はありません。ただ、守らない場合、他の法令に違反する恐れがあります。具体的には、以下の法令違反です。
例えば、電子カルテに権限のない人物が患者情報を閲覧するのは、真正性が確保されていない状態です。患者情報が流出し、個人情報保護法違反につながる恐れがあります。
また、万が一医療過誤や訴訟が発生した場合、三原則を遵守していないと証拠能力や主張の面で不利になる可能性もあります。クリニックの信頼性と安全な医療提供のため、電子保存の三原則の遵守は不可欠といえるでしょう。
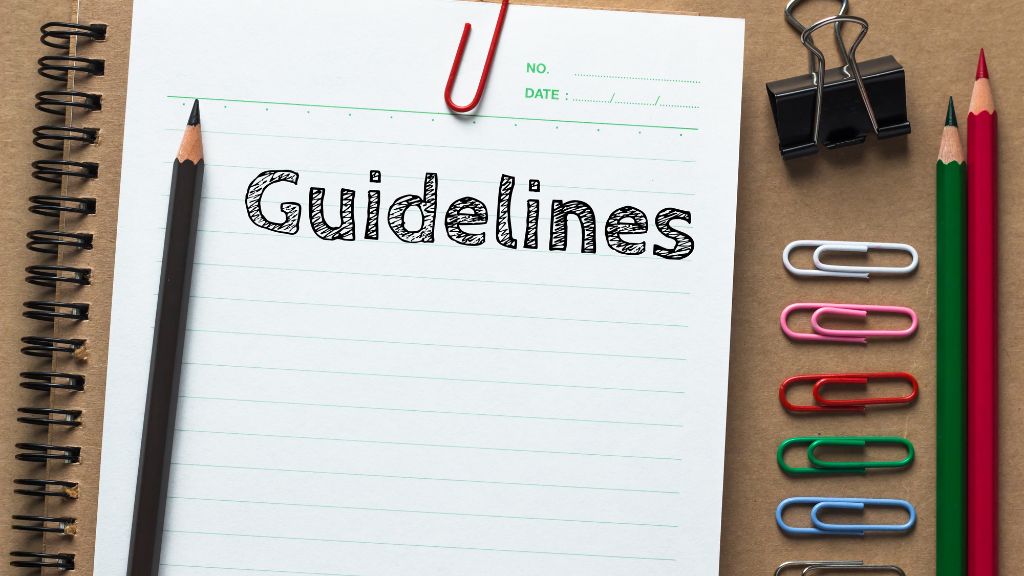
クリニックが遵守すべき電子保存の三原則について、具体的な対策を解説します。
参考:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版本編
カルテの真正性確保のためには、以下の3つのポイントを守り、カルテの正確性を向上させることが求められます。
電子カルテへのアクセス権限を明確に設定し、権限者だけが記録の入力や確定が可能な形で管理する必要があります。例えば、医師や看護師、受付スタッフなど、職種に応じたアクセス権限を設けます。
一度入力、確定された情報は、容易に変更できないシステム設計が必要です。修正が必要な場合は、誰がいつ何の理由で変更したかが記録される仕組みを整えます。
多くの電子カルテでは、自動的に記録する機能がありますが、適切に設定・運用されているか定期的にチェックしましょう。
記録を入力した人、確認した人、承認した人の情報が明確に残るようにします。特に、代行入力の場合(医師が口頭で伝えた内容を看護師が入力するなど)は、確認者と責任者を明示することが重要です。
見読性の確保には、必要な情報を必要なタイミングで提供できるよう、確認可能な状態にしておくことが求められます。例えば、患者からカルテ開示請求があった場合に、診療記録を読める形ですぐに提供できるようにしておかなければなりません。
また、停電やシステム障害などのトラブル時にも、カルテが閲覧可能な状態にしておくことも含まれます。
見読性確保のためには、以下の対策が重要となります。
保存性の確保には、カルテの保存期間中に、何らかのトラブルでデータが消失した場合に復元できる仕組みが求められます。
カルテ情報の保存性が損なわれるリスクとして、以下の3つが挙げられます。
特に、オンプレミス型の電子カルテでは、温度や湿度管理などサーバーの設置環境も損傷の原因となるため、適切な管理が必要です。また、近年医療機関を標的としたランサムウェア攻撃が増加しており、不正アクセス防止の観点からの対策も求められます。
電子カルテの故障やウイルス感染など、適切な保存を妨げるリスクを防止するためには、以下の対策が必要です。

電子カルテの三原則は、カルテ情報を保存する際に求められる真正性、見読性、保存性という3つのルールのことです。セキュリティ対策やアクセス権限、バックアップなど、システム管理面の対策が求められます。
3つの原則を確実に遵守するために効果的なのが、音声入力AIシステムです。音声入力AIにより、医師と患者の音声を自動的に文字に起こします。リアルタイムで正確な記録が残るため、改ざんが入る余地がありません。そのため、カルテの真正性確保に効果的です。
また、カルテデータとは別に音声データの二次保存も可能であり、保存性向上にも効果を発揮します。さらに、音声認識したやり取りは、自動でSOAP形式に要約されて記録できるため、統一されたフォーマットにて見読性も高まります。
電子カルテの音声入力AIシステムに関しては、以下の関連記事で紹介しています。具体的な機能や導入のメリットを解説していますので、ぜひご覧ください。
関連記事:電子カルテの音声入力は役に立つ?AI活用の効果と導入のポイント
ヒーローイノベーションでは、病院やクリニックで活用いただける電子カルテAI音声入力システム「MEDISMA AIクラーク」をご提供しています。無料のオンライン相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
記事を探す
人気記事ランキング
お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせ
MPクラウド(医療経営管理システム)を標準搭載
広告効果を可視化し集患をサポート
最新のホームページで
集患・増患対策を強化します