
- ホームページに関するお問い合わせ
- 050-3645-3907
COLUMN
お役立ちコラム
COLUMN
お役立ちコラム

電子カルテの内容を誤って記載してしまい、修正することは、診療場面ではよく生じます。
しかし、「そのまま修正してもいい?」「そもそも正しい記載ルールは?」とカルテの訂正方法に悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、入力ミスをした際の正しい訂正方法を解説します。さらに、入力ミスが生じる原因と対策についても紹介しています。カルテ入力精度を向上させたいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
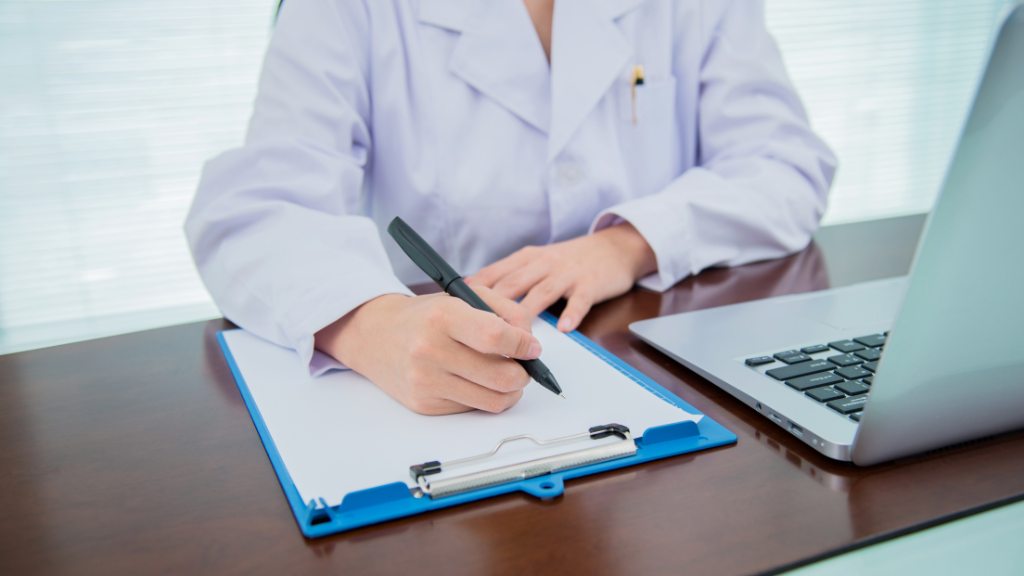
電子カルテ入力時のミスは、どのように生じるのでしょうか。代表的な3つのパターンを紹介します。
外来診療の忙しい時間帯では、患者の混同や処方ミスが生じる場合があります。患者氏名を確認せず、異なる患者のカルテに入力したり、薬の処方を間違えたりするケースです。具体的には、以下のような事例が挙げられます。
患者の混同や処方ミスは、誤った薬剤処方や必要のない検査実施につながり、患者の安全を損なう恐れがあります。また、クリニックの信頼低下や医療訴訟のリスク増大にもつながりかねません。
患者の混同のほかにも、単純な入力間違いもみられます。特に、薬剤量や単位の誤入力は医療事故につながる可能性があります。また、誤った検査オーダーや結果入力ミスは、診断や治療の遅れや病状の悪化につながるでしょう。
3.ダブルチェック不足
重要な処方や検査オーダーに対して、医師と看護師・受付スタッフなどダブルチェックを行うクリニックもあります。しかし、「医師がチェックしているから大丈夫」「看護師が確認しているはず」などの思い込みから、ミスを見逃す場合があるでしょう。

電子カルテの入力ミスに気づいたとき、後から記載内容を修正することはよく起こります。しかし、カルテは適切な方法で訂正しないと「改ざん」とみなされるケースがあるため、注意が必要です。以下の厚生労働省のガイドラインに沿って、正しい修正方法を解説します。
参考:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5.2 版│厚生労働省
電子カルテの訂正で重要な原則が「真正性の確保」です。真正性とは、法的に保存義務がある文書を電子保存する際の条件の一つで、電子カルテの保存には不可欠といえます。具体的には、正当な権限で作成された記録に対し、次の要件を満たす状態と定義されます。
つまり、カルテの内容が正確であり、誰が記載したのかが明確だと、真正性が確保されているといえます。
そのため、カルテの訂正を行う際は、「誰が訂正したのか」「改変した事実が記録されているか」が重要となります。電子カルテに搭載されている履歴保存機能により、訂正履歴を確認できるようにしておくことが必要です。
真正性の確保のためには、以下のように修正履歴や理由がわかるように記録する必要があります。
修正履歴が確認できる方法で訂正を行えば、「意図的な改ざんではない」とみなされることが多いでしょう。
診療時間中に電子カルテを入力できず、事後入力することもよくあるケースです。真正性を保つためには、入力のタイミングについても正確な記録が必要です。
医師法第24条には、「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」と明記されています。「遅滞なく」とは、合理的な範囲での遅れのみ許されるという意味で、よほどの理由がない限り、当日中に記載することが望ましいでしょう。
そのため、可能な限り事後入力は速やかに行うことが大切です。事後入力する場合は、診療とカルテ記載の日時を記録し、遅れた理由を簡潔に記載しておくと、より適切です。
関連記事:電子カルテの事後入力はしてもいい?修正方法と入力効率化の方法を解説

そもそも、電子カルテの入力ミスはどのような原因で生じるのでしょうか。3つの原因について解説します。
多忙な診療時間中は、疲労や時間的なプレッシャーが蓄積し、注意が散漫になりがちです。カルテ入力に時間を割けないと、記録漏れや重複入力が生じやすくなります。
さらに、夜間診療や救急対応時など人員が限られている状況では、ダブルチェックが機能せず、ミスの見落としにつながります。
電子カルテ自体の設計や運用ルールも入力ミスの一つの原因です。使いにくいユーザーインターフェースは、特に忙しい診療時間中にミスを誘発します。例えば、似た名前の薬剤が並んで表示されるシステムでは、選択ミスが起こりやすくなるでしょう。
また、カルテ画面上に表示される患者名が小さかったり、色分けされていなかったりすると、患者の混同リスクが高まります。さらに、同時に複数カルテを開ける設計のシステムでは、タブの切り替え時に患者を混同する可能性があります。
スタッフが電子カルテ操作に慣れていないことで、誤操作が生じる場合があります。特に、機能の多いシステムでは、習得に時間を要するため、操作に不安を抱えるスタッフも少なくありません。
また、教育不足も入力ミスにつながります。電子カルテの入力ルールや安全意識、確認の習慣が院内に浸透していないと、ミスを引き起こします。カルテに携わる全てのスタッフに、入力方法や誤入力のリスクを教育する体系的な仕組みが必要です。

電子カルテの入力ミスは、気づいて訂正することで医療的なリスクを防止できます。しかし、そもそも入力ミス自体を減らす方法があれば、より安全性が高い運用が可能でしょう。電子カルテの入力ミスを減らす3つの方法を解説します。
患者の混同が生じないよう、診療業務の流れを見直しましょう。具体的には、次のような点をルール化し、スタッフに徹底させていくことが大切です。
【カルテ使用時】
【処方、検査オーダー時】
医師だけでなく、看護師や医療クラークなど、複数のスタッフでタスクシェアをしながら、何重にもチェックする体制をつくりましょう。
人的なミスを防止するため、スタッフへの研修を行い、意識向上をはかります。操作に関するトレーニングに加え、インシデントやヒヤリハット事例を共有し、防止策を学びます。
ヒューマンエラーの防止に大切なのは、「ミスを責めない風土づくり」です。ミスを学ぶ機会として、スタッフから積極的にヒヤリハット事例を挙げてもらいましょう。日常業務でミスを認識する習慣がつき、自発的に防止できるようになるでしょう。
カルテ入力を自動化できる音声入力システムを導入すれば、入力ミスを減らせます。AIを活用した音声入力システムは、診察内容を全て録音し、SOAP形式に自動的に要約できます。
リアルタイムで入力でき、医師の入力負担が軽減されるでしょう。
関連記事:電子カルテの音声入力は役に立つ?AI活用の効果と導入のポイント

電子カルテの入力ミスは、ガイドラインに沿った正しい訂正方法で行うことが求められます。また、カルテ業務の見直しやスタッフへの教育研修を行い、入力ミスを減らす対策も重要です。
特に、AI音声入力など、カルテ入力を自動化できるツールを導入すれば、入力ミスの減少につながります。ヒーローイノベーションでは、病院やクリニックで活用いただける電子カルテAI音声入力システム「MEDISMA AIクラーク」をご提供しています。無料のオンライン相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
記事を探す
人気記事ランキング
お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせ
MPクラウド(医療経営管理システム)を標準搭載
広告効果を可視化し集患をサポート
最新のホームページで
集患・増患対策を強化します