
- ホームページに関するお問い合わせ
- 050-3645-3907
COLUMN
お役立ちコラム
COLUMN
お役立ちコラム

医療機関では、患者対応の忙しさから電子カルテをリアルタイムで入力できず、診療後にまとめて記録するケースがあります。
しかし、まとめて記録する「事後入力」が法的に問題がないのか心配になる医師や医療従事者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、電子カルテの事後入力に関して、厚生労働省のガイドラインをもとに正しい修正方法を解説します。また、事後入力は記録の正確性に支障をきたすことに加え、業務負担の増大にもつながります。カルテ入力効率を向上させる方法も解説しますので、電子カルテの入力に悩みがある方は、参考にしてみてください。
目次

事後入力は望ましくないとわかっていながらも、診療後に入力せざるを得ないケースがあります。
事後入力の法的な問題性や記載ミスの修正、医師以外の入力について解説します。
参考:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5.2 版 本編│厚生労働省
診療中にカルテ記載ができなかった合理的な理由があれば、事後入力でもやむを得ないと考えられます。医師法第24条には、「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」と定められています。
「遅滞なく」とは、合理的な理由での遅れは許容されるという意味です。「緊急対応でカルテ記載ができなかったため、当日中に事後入力した」という場合は合理的な範囲といえます。実際の診療時間と入力が遅れた理由を付記しておくとよいでしょう。
一方で、「週末にまとめて記入する」のは、「遅滞なく」の範囲を超え、不適切とされる可能性があります。事後入力する際は、カルテを書くまでの時間や理由記載への配慮が求められます。
適切な管理のもとであれば、事後の修正ができます。具体的には、カルテの改ざんとみなされないように記載することが必要です。
改ざんかどうかの判断には、カルテの「真正性の確保」が重要となります。電子データの保存について定めたe-文書法省令では、以下のように記録の保存には「真正性の確保」が求められています。
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。
出典:厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(第4条第4項第2号)│e-Gov法令検索
「真正性」とは、電子カルテ内容の正しさを保証できるようにしておくことです。真正性の確保のため、事後に修正する際には、以下のように修正履歴の保存が必要です。
修正の責任者を明確にし、カルテを改ざんしたとみなされないように修正しなければなりません。電子カルテには、修正履歴が記録され、修正者がわかるようになっているため、この点はクリアしているといえるでしょう。
カルテ入力まで手が回らない場合、看護師や医療クラークなどのスタッフが診察時に代行入力するケースもあるでしょう。代行入力は、適切な運用方法のもとで可能です。
厚生労働省の「医療情報システムの安全管理ガイドライン」では、代行入力の際には以下の点に留意するよう推奨されています。
| 留意点 | 説明 | 具体例 |
| 運用規程の整備 | 代行を認める具体的な業務や誰が誰を代行するかを規程で定める | 診察時の医師のカルテ入力を看護師が代行する |
| 管理情報の記録 | 代行入力時に誰の代行がいつ誰によって行われたかを、都度記録する | 看護師が代行入力した内容と日時をカルテに記録 |
| 確定操作の実施 | 代行入力により記録されたカルテ内容は、速やかに確認して承認を行う | 看護師が入力した内容を医師が確認して確定する |
上の表のように、運用方法をルール化し、代行入力の内容と日時が正しく記録される仕組みをつくる必要があります。特に、代行入力された内容の責任は医師にあり、内容をきちんと確認した上で承認することが求められます。
関連記事:【違法ではない】電子カルテの代行入力で業務の負担を減らすには?
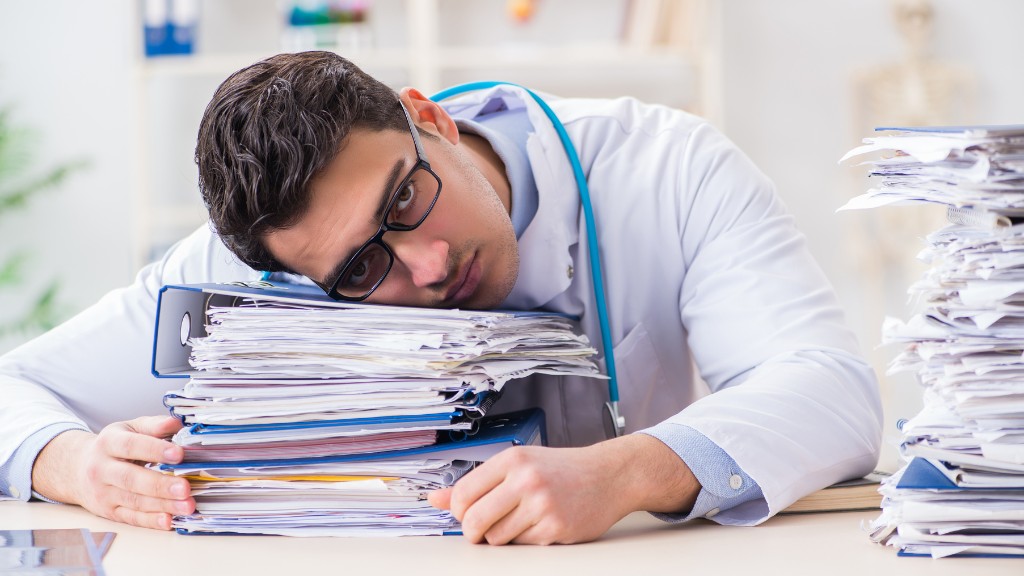
電子カルテの事後入力は、ガイドラインに準拠した適切な方法で行えば問題はありません。しかし、事後に入力することで、以下のような業務上のデメリットが生じ、スムーズな診療の妨げになる恐れがあります。事後入力によるデメリットについて解説します。
診察内容が入力されていないと、医師以外のスタッフに必要な情報がスムーズに伝わらず、連携に支障をきたします。例えば、患者が受付に「今日はお薬を変えてもらったのですが、変わっていません」という申し出があった場合、カルテに記載がなければすぐに返答できません。診察中に医師に確認する必要が生じ、患者を待たせることになります。
患者対応に必要な情報がスタッフ間で共有できず、提供する医療の質が低下してしまいます。
診察後にまとめてカルテを事後入力する場合、患者とのやりとりを思い出すのに時間がかかり、結果的に業務効率が下がります。
また、後回しにしても入力時間は限られているため、記載内容が簡略化されるなど、カルテの質も低下しがちです。カルテの質低下は、治療方針の質にも影響します。患者に対して適切でない対応をしてしまい、適宜方針の修正が必要となるなど、手間が生じる可能性があります。
診療内容をあいまいな記憶で書いてしまうと、記載間違いや他の患者との混同が生じやすくなります。カルテ記録の正確性が損なわれ、訴訟や監査時などに法的なリスクが高まります。
例えば、患者からカルテ開示請求があった場合、記載間違いがあったことが明らかになります。訴訟に発展した際には、医療機関側が不利になる可能性があるでしょう。
また、事後入力により、診療日と記録日にずれが生じることもリスクにつながります。訴訟時に裁判所から不利な解釈をされたり、保険請求時の減点があったりする恐れがあります。

電子カルテの事後入力は、業務効率や患者対応の質、法的リスクにも影響を及ぼします。やめた方がいいとわかりながらも、診療の中で事後入力せざるを得ないほど忙しい場合、どうすればよいのでしょうか。
カルテ入力を効率化し、事後入力を減らす方法として、以下の3つを紹介します。
カルテの入力を看護師や医療クラークなどの他のスタッフと分担することで、医師の負担を軽減します。特に、診察中の記録代行を担う医療クラークの外来への配置は、医師の増員よりも業務効率化に効果があることがわかっています。
医療知識が必要な診察前の予診は看護師が担当し、診察中は医療クラークがカルテ入力を行えば、医療の質を落とさず効率化できるでしょう。
参考:令和2年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和2年度調査)の報告案について│厚生労働省
関連記事:医療クラーク(メディカルクラーク)とは?医療事務との違いや電子カルテ入力など業務を解説
クラウド型電子カルテとは、カルテのデータを院内ではなくクラウド上で管理するシステムを指します。インターネット環境があれば使用できるため、PCやタブレット、スマートフォンなどさまざまなデバイスでアクセス可能です。移動中や空き時間にカルテ記録が残せるため、事後入力を分散できます。
また、タブレットから電子カルテにアクセスすれば、写真で記録を残せるため、画像の取り込みなども必要なくなります。例えば、以下のような記録を効率化できるでしょう。
診察室での活用はもちろん、訪問診療などのPCがない環境下でもスムーズに情報を記録でき、カルテ入力の効率化につながります。
AIによる音声入力システムを活用すると、診察時のやりとりを自動で記録化できます。やりとりが全て録音され、内容がSOAP形式で要約されるため、診察中のカルテ入力の必要がなくなります。また、要約後に手動での編集が可能なので、診察スタイルに合わせて活用可能です。
AI音声入力により、カルテの正確さを保ったまま、入力作業の負担を軽減できるでしょう。電子カルテのAI音声入力システムに関しては、以下の関連記事も参考にしてみてください。
関連記事:電子カルテの音声入力は役に立つ?AI活用の効果と導入のポイント

電子カルテの事後入力は、記載内容の真正性を保ち、遅滞なく記録するよう注意することで、大きな問題とはなりません。しかし、記載内容が共有されず、スタッフの対応や業務効率に影響を及ぼします。また、あいまいな記憶から正確性が担保されず、法的リスクにつながる可能性もあるでしょう。
診療の質を保つためには、事後入力ではなくリアルタイムで入力できる対策が求められます。他のスタッフとのタスクシェアを試みつつ、クラウド型電子カルテや音声入力AIの活用を検討しましょう。
特に、音声入力AIは診察内容を自動入力できるため、カルテ入力自体を大幅に効率化できます。ヒーローイノベーションでは、病院やクリニックで活用いただける電子カルテAI音声入力システム「MEDISMA AIクラーク」をご提供しています。無料のオンライン相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
記事を探す
人気記事ランキング
お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせ
MPクラウド(医療経営管理システム)を標準搭載
広告効果を可視化し集患をサポート
最新のホームページで
集患・増患対策を強化します