
- ホームページに関するお問い合わせ
- 050-3645-3907
COLUMN
お役立ちコラム
COLUMN
お役立ちコラム
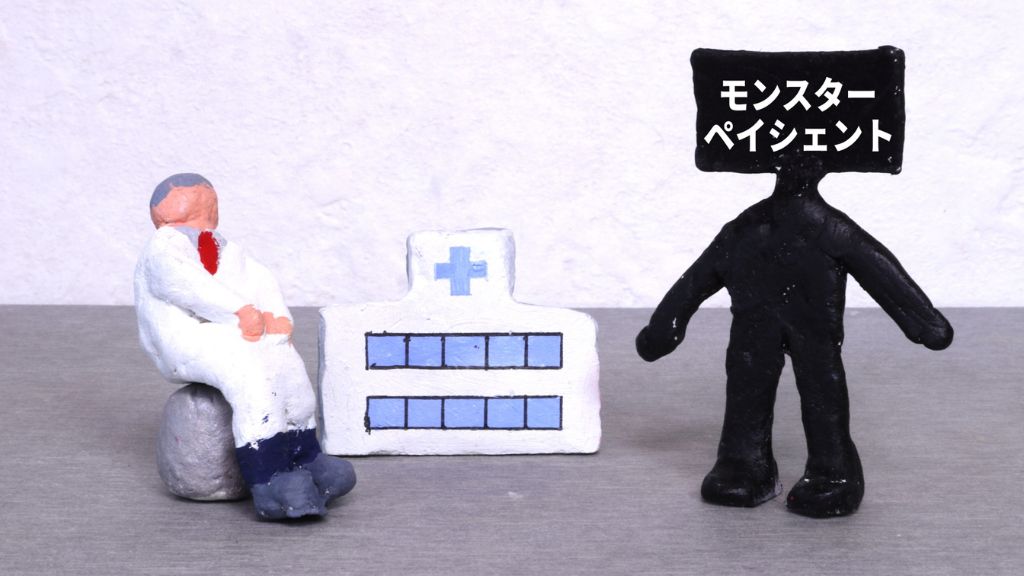
ペイシェントハラスメントとは、患者やその家族からの暴言や暴力、不当な要求を指します。診療の妨げになるだけでなく、スタッフの精神的負担や離職の原因にもなる問題です。
「どこからがハラスメントか判断しづらい」「具体的な対処がわからない」などと悩むクリニックの経営者や開業医の先生も多いでしょう。
本記事では、ペイシェントハラスメントの定義や該当する行為、事例、具体的な対処の流れを解説します。さらに、近年注目されているAI音声入力を活用した証拠保全の方法も紹介しています。ペイシェントハラスメントの具体的な対応ルールをつくりたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次

ペイシェントハラスメント(ペイハラ)とは、患者やその家族から医療従事者に対する暴言、暴力、理不尽な要求を指します。株式会社エムステージが医師を対象に行った調査では、69.6%がペイシェントハラスメントの経験があると回答しました。
治療方針や内容に対するものが最多で、その他には医師の言動や待ち時間、診断・検査結果などが原因でした。診療場面では、ペイシェントハラスメントは珍しくないものといえます。
ペイシェントハラスメントの具体的な判断基準や事例、原因について掘り下げて解説します。
参考:「ペイシェントハラスメント」について、アンケート調査を実施 | エムステージ
ペイシェントハラスメントに関する国の明確な指針はありません。ただ、厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルでは、以下の2点から判断することが推奨されています。
【該当例】
【該当例】
具体的には、以下のような言動や行為がペイシェントハラスメントに該当するでしょう。
ただし、厚生労働省のマニュアルでは「どこまでをハラスメントとするかは、企業の業種や業態、企業文化によって異なる」としています。自院の特徴を把握した上で、上記のような判断基準をもとに、独自の基準を設定し、院内に周知することが大切です。
参考:カスタマーハラスメント対策企業マニュアル│厚生労働省
ペイシェントハラスメントとしては、待ち時間や治療・診断に対する不満が多い傾向にあります。2つの架空事例を紹介します。
混雑する外来で、1時間待った患者Aさんのカルテが他の患者のファイルに紛れてしまった。さらに30分待たされたAさんが看護師に確認するとミスが発覚した。
看護師が「次にご案内します」と伝えるも、Aさんは「今すぐ診察しろ」「土下座して謝罪しろ」と声を荒げて、周囲の患者も不安そうな表情に。
看護師は一人で対応を続けていたが、先輩看護師が気づいて複数人での対応に切り替えた。静かな個室に誘導し、特別対応はできない旨を伝えたが、Aさんは納得できず不満を述べ続けた。最終的には、クリニックから退去をお願いし、帰ってもらった。
整形外科に通うCさんに医師は検査の必要があると診断したが、自院には必要な設備がなく、他院への紹介受診を勧めた。しかし、Cさんは「できもしない検査を勧めるのか」と不満を訴え続け、数十分居座り続けた。
説明を繰り返してようやく退出できたものの、後日レビューサイトに事実に基づかない誹謗中傷の投稿を繰り返すようになった。クリニック側は証拠を集め、法的対応を検討。弁護士に相談して警告文書を送付した。

ペイシェントハラスメントが発生した場合、どのように対応すればよいのでしょうか。発生時に冷静な対処ができるよう、以下の5つのポイントを意識しましょう。
患者からの暴言や理不尽な要求があれば、まずはスタッフの安全確保を最優先します。患者と適切な距離を保ち、可能であれば複数スタッフでの対応に切り替えましょう。
怒っている患者を刺激しないよう、要求を一旦傾聴するなど共感的な姿勢が大切です。例えば、「お気持ちはよく理解できます」などと伝えながら、怒りの収束を待ちましょう。
クリニック側に非があるかどうか判断できない点については、安易に謝罪をしないことが大切です。事実確認が取れないまま謝罪すると、ミスを認めたことになり、その後の対応で不利となる可能性があります。
「ご不便な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした」と患者の気持ちに対して謝罪する対応が望ましいでしょう。また、困難な要求は「院内で検討します」と伝えるなど、その場で判断しないことが大切です。
怒っている患者に対し「静かにしてください」「他の方に迷惑です」と伝えると、さらなる怒りの火種になりかねません。「お話をしっかり聞きたいので、静かな個室に移動しましょう」と相手のニーズに合わせて提案すると聞き入れてもらいやすいでしょう。
いくつか提案をしても聞き入れてもらえない場合、警察への通報を検討します。
トラブル解決や再発防止のため、客観的な証拠を残しましょう。具体的には、損害賠償請求などのため、以下のような証拠が必要です。
事案終了後には、記憶が新しいうちに関係するスタッフへのヒアリングを行います。5W1Hの形式で事実を整理しましょう。また、暴力行為があった場合、けがの生活への支障度など、主観的な情報も聞き取っておくと有力な証拠となります。
ただし、スタッフを追い詰めたり責めたりしないように注意しましょう。「あなたの対応にも問題があったのでは」などの発言をせず、事実だけを明確にするよう聞き取ることが大切です。
長時間の居座り、暴力行為などがみられる場合は、以下のように注意や退去の指示をしましょう。その上で、警察に通報することを予告し、通報します。
迷惑行為が繰り返される場合は、文書でやめるよう通告を行うことも有効です。また、被害が生じている場合は、集めた証拠をもとに、損害賠償請求を行うケースもあります。自院での対応が難しい場合、弁護士に相談し連携して対応しましょう。
参考:苦情対応ハンドブック│国立大学附属病院医療安全管理協議会

ペイシェントハラスメントの発生や、その後のトラブル防止のためにできる対策として、以下の3つが挙げられます。
ペイシェントハラスメントに関する方針を定め、患者やスタッフに周知しましょう。具体的には、以下の点を含めた方針を策定します。
【ハラスメント行為の定義と具体例】
【ハラスメント行為への対応】
院内の目立つ場所にポスターを掲示したり、ホームページに記載したりするなど、患者の目にとまりやすい方法で周知します。スタッフに対しては、対応マニュアルを作成し、全スタッフが一貫した対応ができる体制を整えましょう。
ハラスメント事例を院内で共有し、再発防止策を全体で考えるシステムを構築しましょう。事例共有では、原因を個人の対応にするのではなく、組織全体の問題として捉えることが大切です。
「対応が悪かった」よりも「システムをどう改善するか」に焦点を当てることで、安心して事例共有ができる環境をつくります。
証拠の確保やハラスメントの抑止として、防犯カメラの設置は効果的です。受付や待合室、診察室などの主要な場所に設置しましょう。
また、診察中のやりとりを録音し、自動的にカルテに要約されるAI音声入力システムの活用もおすすめです。会話の内容がすべてクラウド上に保存されるため、後から具体的なやりとりを確認できます。患者が主張する内容と異なる事実があれば、客観的な対応が可能となります。
関連記事:電子カルテの音声入力は役に立つ?AI活用の効果と導入のポイント

クリニックの安全と効率化を同時に実現できるのが「MEDISMA AIクラーク」です。
パーソル総合研究所の調査によれば、ペイシェントハラスメント対策を実施している医療機関は、未実施と比較して離職率が7.8%低いことが明らかになっています。しかし、39.7%の医療機関ではまだ対策が行われていませんでした。ペイシェントハラスメント対策は、人材確保のために必要な施策ですが、十分に行えている病院・クリニックは未だ少ない現状があります。
AIクラークは、診察中の会話を録音・クラウド保存する機能により、客観的証拠として活用できます。さらに、やりとりが自動的にSOAP形式で要約されるため、患者と話をするだけでカルテが完成します。
単にハラスメント対策としてだけでなく、効率化の手段としても活用可能です。ペイシェントハラスメントに加え、効率化するシステムとして、導入を検討してみてはいかがでしょうか。詳しくは無料オンラインデモで体験いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
参考:カスタマーハラスメントに関する定量調査│パーソル総合研究所
記事を探す
人気記事ランキング
お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせ
MPクラウド(医療経営管理システム)を標準搭載
広告効果を可視化し集患をサポート
最新のホームページで
集患・増患対策を強化します